近年、社会の変化と住民ニーズの多様化に伴い、「自治体DX」という言葉を耳にする機会が増えました。自治体DXとは、単なるデジタルツールの導入にとどまらず、行政のあり方そのものを変革する重要な取り組みです。
本記事では、自治体DXの基本的な概念から、現在直面している課題、そしてその推進に向けた具体的なポイントまで、わかりやすく解説します。

Contents
はじめに:自治体DXとは
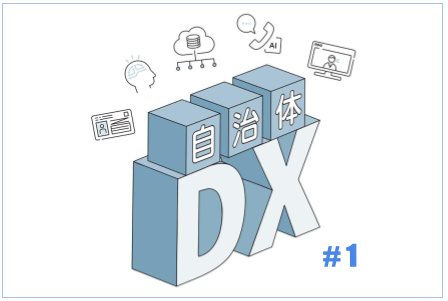
DX(Digital Transformation)は、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織文化、業務プロセスを変革し、競争優位性を確立する取り組みを指します。これを自治体に当てはめたものが「自治体DX」で、デジタル技術とデータを最大限に活用し、住民サービスの向上と行政運営の効率化を図り、地域社会の課題解決と魅力向上を目指しています。
なぜ今、自治体DXが必要とされているのでしょうか。大きな背景には、少子高齢化による人口減少と行政職員の不足があります。限られたリソースの中で、多様化する住民ニーズに対応し、持続可能な行政サービスを提供するためには、業務の効率化と生産性向上が不可欠です。また、新型コロナウイルスの影響で、行政手続きのオンライン化やリモートワークの必要性が高まったことも、DX推進を加速させる要因となっています。
総務省も「自治体DX推進計画」を策定し、全国の自治体におけるデジタル化を強力に後押ししています。
外部リンク:総務庁「自治体DXの推進」のページ
自治体DXの現状と課題
自治体DXはいますぐ取り組むべき課題とも言えますが、その道のりには多くの課題が存在します。まず、多くの自治体に根強く残るアナログ文化とデジタル化の遅れが挙げられます。紙媒体での業務や押印文化、複雑な内部手続きが、デジタル化の足かせとなっています。
次に、DXに対する理解不足とデジタル人材の不足は深刻な問題です。専門知識を持つ職員が少なく、外部からの人材確保も容易ではありません。ITベンダー任せになりがちで、自治体内部でのDX推進をリードする人材が不足しているのが現状です。
さらに、行政と住民とのコミュニケーション不足も課題です。住民がデジタルサービスに慣れていないケースや、自治体側からの情報発信が不足していることで、デジタルサービスの利用が進まないという問題も抱えています。
自治体DX推進のポイントとアプローチ
自治体DXを成功させるためには、計画的かつ多角的なアプローチが必要です。まず、総務省が示す「自治体DX推進計画の策定」とその中の「重点取組事項」に沿って、具体的な目標とロードマップを明確にしましょう。
推進の柱は、以下の点です。
業務効率化と生産性向上の実現:
AIやRPA(Robotic Process Automation)といった技術を活用し、定型業務の自動化やペーパーレス化を進め、職員がより住民サービスに集中できる環境を創出します。
行政サービスの利便性向上と情報公開の迅速化:
住民が窓口に行かなくても、オンラインで手続きを完結できる仕組みを拡充し、必要な情報をタイムリーに公開することで、利便性を高めます。
多言語対応やユニバーサルデザインによる「誰でも利用しやすいサービス」の提供:
デジタルデバイド*を解消し、高齢者や障がい者、外国籍住民など、誰もがデジタルサービスを利用できる環境を整備します。
*デジタルデバイド:デジタル機器の利用格差、デジタル格差
新たなサービスの創出:
収集したデータを分析し、住民ニーズに合わせたきめ細やかな行政サービスや、地域課題を解決する新規サービスを企画・実行します。
自治体DXの成功事例
全国の自治体では、さまざまなDXの取り組みが成果を上げています。
デジタルガイド導入による問い合わせ削減:
AIチャットボットやFAQシステムを導入し、住民からの簡単な問い合わせには自動対応することで、職員の負担を軽減し、住民の待ち時間を削減しています。
AIチャットボットの導入による住民対応の効率化:
住民からの質問に24時間365日対応可能なAIチャットボットを導入し、問い合わせ対応の質とスピードを向上させています。
RPAによる業務自動化:
住民票発行の補助業務やデータ入力作業など、定型的な業務をRPAで自動化し、職員の生産性向上とヒューマンエラーの削減を実現しています。
タブレット導入によるペーパーレス会議の実現:
議会や会議で紙の資料配布を廃止し、タブレット端末を活用することで、印刷コストや配布作業の削減、資料のリアルタイム共有、保管スペースの効率化を実現しています。
保育現場でのICTシステム導入による業務効率化:
保育園における登降園管理や連絡帳、園児情報の記録などをタブレットやスマートフォンで行うICTシステムを導入。保育士の事務負担が減り、園児と向き合う時間が増加することで、現場の生産性と質の向上につながっています。
その他、先進的な取り組み事例は、CLOMO 事例ページでも多数ご紹介していますので、ぜひご参照ください。
より安全で効率的な自治体DXへ:MDM導入のメリット
自治体DXを進める上で、職員が利用するスマートフォンやタブレットといったモバイルデバイスの活用は欠かせません。これらのデバイスがあれば、庁舎内だけでなく、災害現場や外出先など、場所を問わず業務を進められ、住民サービスの迅速化にもつながります。
しかし、多くのデバイスを適切に管理・運用しなければ、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。そこで重要になるのが、MDM(Mobile Device Management:モバイルデバイス管理)です。MDMを導入することは、自治体が抱えるこれらの課題を解決し、より安全で効率的な自治体DXを実現する鍵となります。
MDMを活用することで、デバイスのセキュリティを大幅に強化し、管理を劇的に効率化できます。具体的には、万が一デバイスを紛失・盗難した場合でも、遠隔からのロックやデータ消去(リモートワイプ)で情報漏洩リスクを最小限に抑えられます。
また、パスワードポリシーの強制や不正アプリの検知・ブロックにより、強固なセキュリティを維持できます。さらに、多数のデバイスの設定やアプリ配布を一元的に行うことで、IT担当者の運用管理にかかる手間を大幅に削減し、業務の効率化につながります。これにより、自治体DXの基盤をより盤石にできるのです。
まとめ
自治体DXは、高齢化や多様化する住民ニーズに対応し、持続可能な行政を築くために、いま、最優先で取り組むべき課題です。多くのハードルを乗り越え、DXを成功させるには、計画的なアプローチとデジタル技術の賢い使い方が不可欠です。
特に、職員が使うモバイルデバイスの普及が進む中で、MDMによる堅牢なデバイス管理は、自治体DXの強力な推進力となるでしょう。
関連ページ:モバイル導入で自治体DXを加速 安全で効率的な運用をお手伝い
関連記事:
・ガバメントクラウドへの移行戦略
・自治体情報セキュリティガイドラインへの具体的な対応と運用
さまざまなMDMサービスが展開されている中で、CLOMO MDMはMDM市場で14年連続シェアNo.1*を誇っています。
CLOMO MDMは、豊富な機能の搭載、幅広いデバイスへの対応、わかりやすく使いやすい管理画面が特徴です。また、ISMAPにも登録しており、高いセキュリティ基準を満たしています。国産のMDMサービスのため特にサポート面が手厚く、メーカーからの直接サポートや電話サポートを受けられます。24時間365日、電話で有人オペレータが緊急対策の代行も行っています。製品の機能・活用事例のダウンロードや製品についてのお問い合わせもできるため、ぜひご活用ください。
あらゆる業界で利用されており、企業はもちろん、学校や病院などの教育機関や医療機関への導入事例も豊富です。市場シェアNo.1*のCLOMO MDMで、安心・安全なデバイス管理を行いましょう。
*出典:デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション/コンテンツ・モバイル管理パッケージソフトの市場展望」2011〜2013年度出荷金額、「MDM自社ブランド市場(ミックITリポート12月号)」2014~2023年度出荷金額・2024年度出荷金額予測

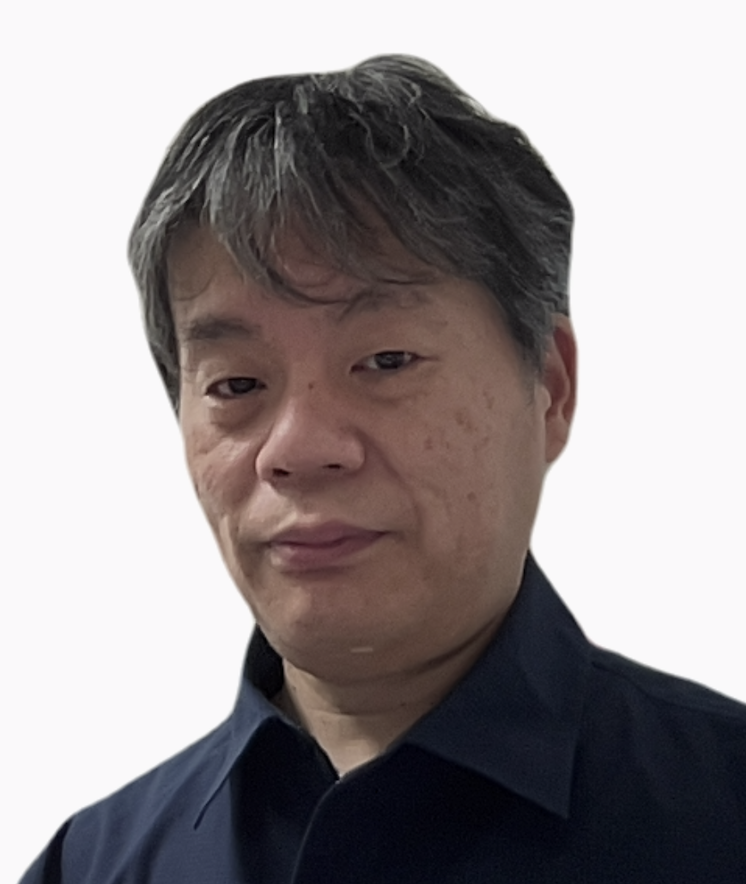
監修者
岩井 朋弘
CLOMO事業本部 営業部
2022年にCLOMO事業本部 営業部に入社。前職では地方公共団体向けに行政システム販売、BPOサービスの提案営業を担当し、業務効率化のための業務分析やBPOサービスの改善、業務システムの企画に携わる。現在はその経験を活かして自治体DXを推進するべく、自治体および官公庁を中心にデバイス・MDM活用の提案を行っている。






